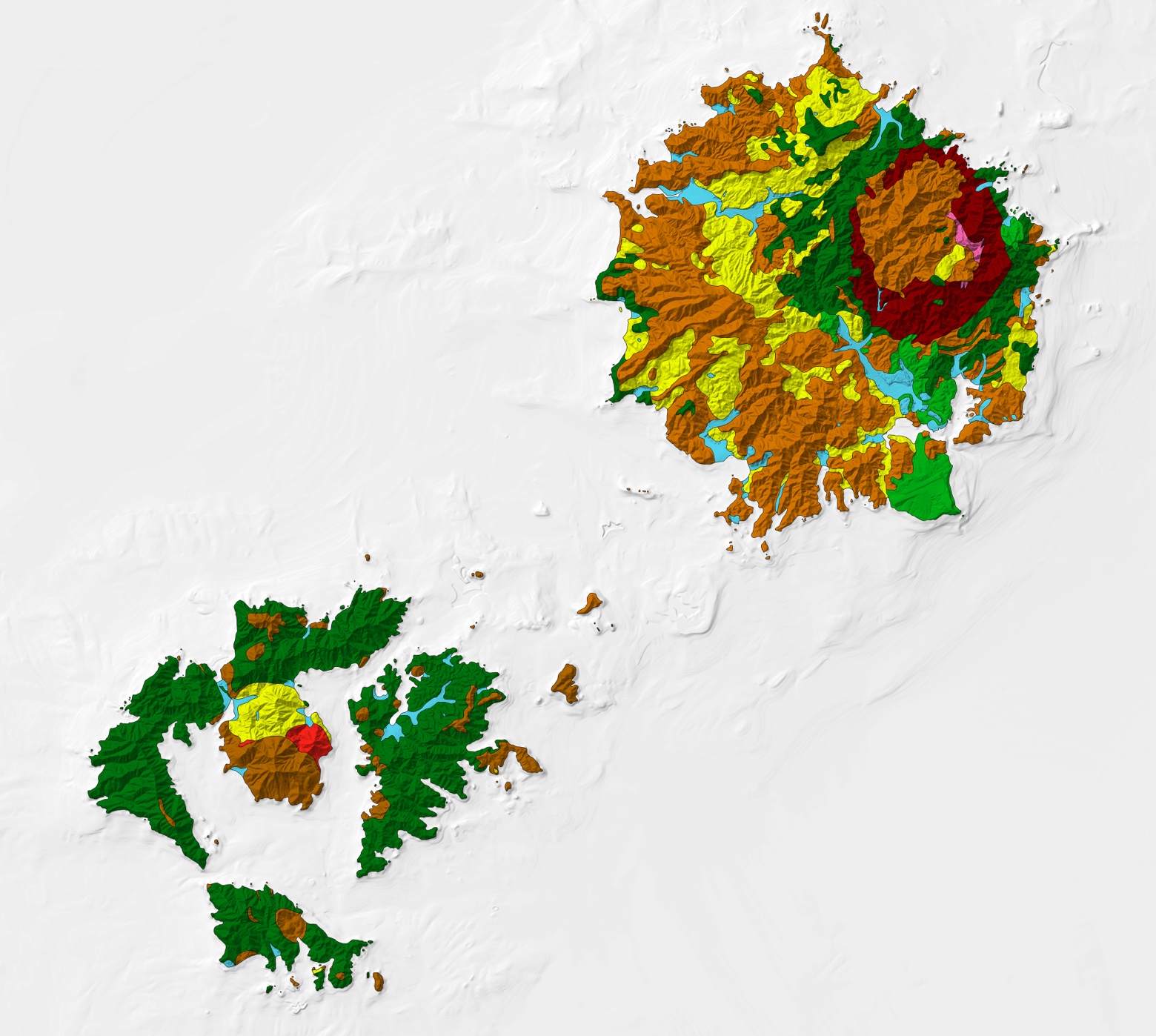隠岐諸島は、時代によってその姿を“七変化”させてきた歴史があります。
世界的に見ても珍しい不思議な生態系、隠岐ならではの歴史・文化が生まれる元となった、その成り立ちを解説します。
1
2
3
4